CHAPTER - 01研究テーマ
より良い世界を実現する
イオン伝導体の創出を探求
研究テーマ
アニオンの複合化で拓く
固体イオニクスのフロンティア
研究対象のイオン伝導体について簡単に教えてください。
固体であっても、その中を構成元素がまるで液体のように流れるユニークな物質群が存在します。流れる元素はイオンの形で移動するため、これらの物質はイオン伝導体と呼ばれます。安全で高速充放電が可能な次世代電池として注目されている全固体電池や、脱炭素社会における蓄エネルギーデバイスの急先鋒である燃料電池の実現に不可欠な物質で、環境計測センサーやエレクトロ二クス材料にも利用されており、ひいては水素やアンモニアの合成にも重要な役割を果たします。循環可能な社会の実現にむけて、私たちはこのユニークな物質を深く理解し、その理解に基づいた物質のデザインによって、より高い機能を発現する材料を創り出すことを目指しています。
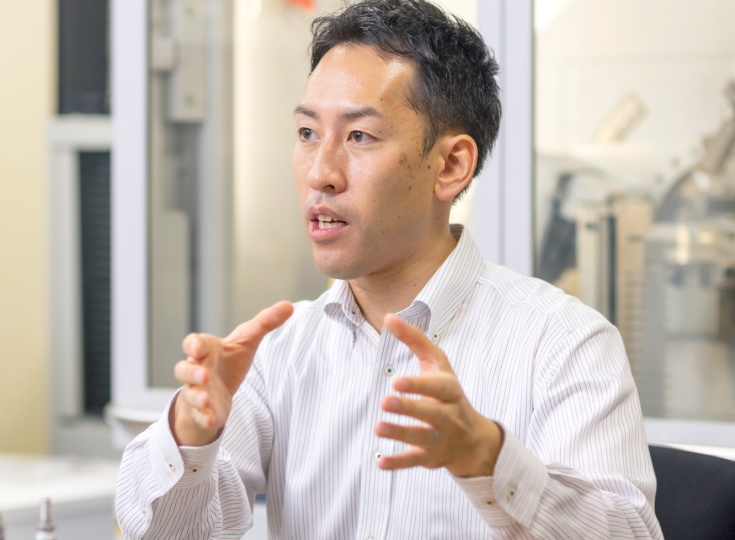
ユニークな物質を深く理解し
知識の体系化を進めていく
研究分野の中ではどのような位置づけの研究をされているのでしょうか?
イオン伝導体設計のコツの1つは、固体内でイオンが流れる経路の周辺を上手に設計することです。経路周辺には、古くは酸素、2010年代ごろからは硫黄、そして2018年以降はハロゲンが組み込まれ、それらの物質が探索の主戦場でした。しかし複数種類の元素を経路周辺に組み込む物質設計により、爆発的に複雑な物質・経路が可能となります。元素の複合による広大な物質空間は未だ見ぬ新物質がたくさん隠れている魅力的な領域ですが、同時に複雑な経路をどう設計するか頭を悩ませることになります。今世界は実験先行で進んでいますが、狙った機能を発揮する物質を効率よく設計するためには機能発現のメカニズム解明がとても重要です。私たちは実験で変化が得られた時に「なぜその変化が起こるのか」を解明し、深い理解に基づく知識の体系化を目指しています。「どうすれば世界をよりよくするイオン伝導体を創れるのか」、この問いに答えるための研究を展開しています。
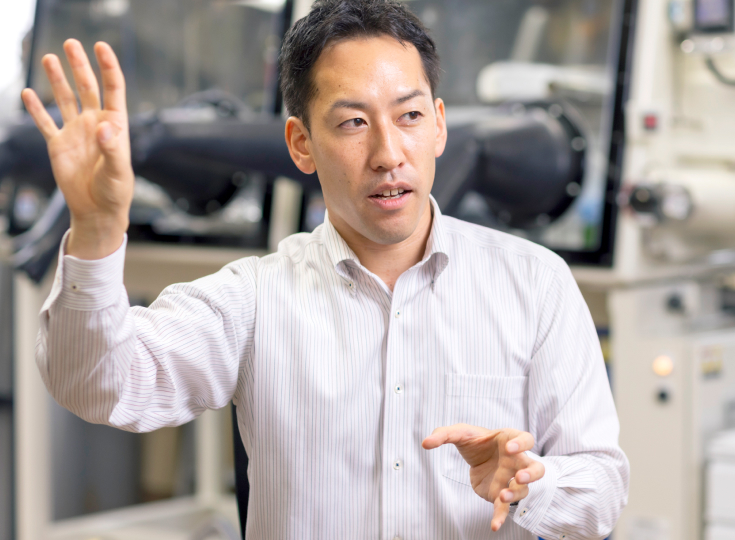
CHAPTER - 02研究の魅力
自ら設計した物質によって世界をより豊かにできる
研究テーマの魅力は何でしょうか?
循環可能な社会の実現に向けてクリーンなエネルギーがそこかしこで生み出されたとしても、作り出したエネルギーを利用する場所まで運び、蓄えておくためには蓄エネルギーデバイスが必要不可欠です。現時点ではリチウムイオン電池がその役割を担っていますが、より安全で高性能な蓄エネルギーデバイスが実現できれば世界を変える可能性があります。自分が携わった研究が、それらの物質の設計などに利用され、貢献する事態をこの目で見ることができれば、研究者としてこれほどうれしいことはありません。
とはいえ、日々の研究活動は緻密かつ地味なものです。「この物質だったらうまくいくだろうか」とトライ&エラーを繰り返し、「どうしてうまくいくのか、あるいはうまくいかないのか」を考え続けていますが、同僚や研究仲間、異分野の研究者と話している時に突如新しいアイデアがひらめくことがあります。そうやって少しずつ前進していくことに、研究者として楽しさを感じます。
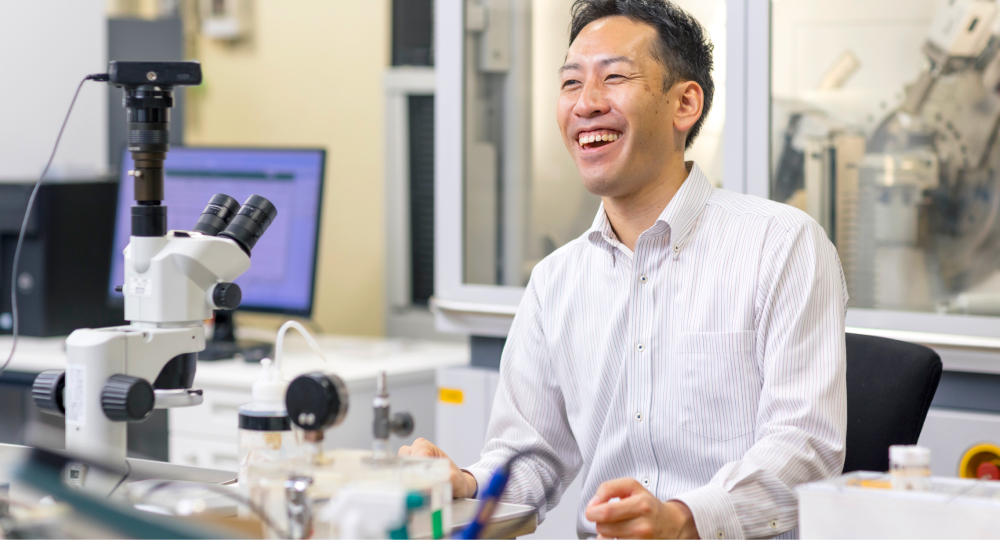
研究を進めて行く中でこれまでに経験した一番大きな壁はどのようなものだったのでしょうか?
そうですね。博士のころ二本目に出した論文の時です。
同じ材料で同じものを作っているつもりなのに、すごくいいのができたり、ダメだったり性能にばらつきが出る。その理由が全く分からなくて何カ月も悩みました。最先端の論文を読み漁ったけれども説明ができなくて、一回勉強し直そうと思って昔の教科書からやり直しました。最終的には1800年代にギブスが提唱した熱力学、授業でしかやらないような古典的な理論を使うと、今まで悩んでいた性能のばらつきが全部説明できることに気づきました。言われれば誰でも分かるけど、最先端の現場で誰も考え付かなかったメカニズム、これに気づいた時の興奮は計り知れないものがあります。一周回って新しい実験コンセプトに名前を付け、その重要性を再度提唱しました。後続の論文を著名雑誌に出しましたがいろんな人に「面白いね」と言ってもらえ、現在では熱電の分野においてその実験コンセプト名が定着しつつあります。これは、研究って面白いと、その醍醐味を教えてくれた壁であり、連綿と続く人類の探究活動の文脈の中で、私自身の研究者としての出発点となった原体験だと思います。
CHAPTER - 03理想の研究者
世界の潮流にのりながら
新しい切り口での研究を続けたい
こんな研究者になりたいという人物像はありますか?
研究者としては「おもしろいことをやっている」と言われるような研究を続けていきたいです。この“おもしろい”とは、いろいろな意味が含まれています。例えばさまざまな研究結果や知見を統合したり、まったく新しい切り口を提示したり、これまで誰もやってこなかったアプローチで結果を出すことが、おもしろさの一つの形だと考えています。自分が面白がってやっている研究を、後に続く人たちに「おもしろそう」と思ってもらえる研究者が、目指す人物像の一つです。
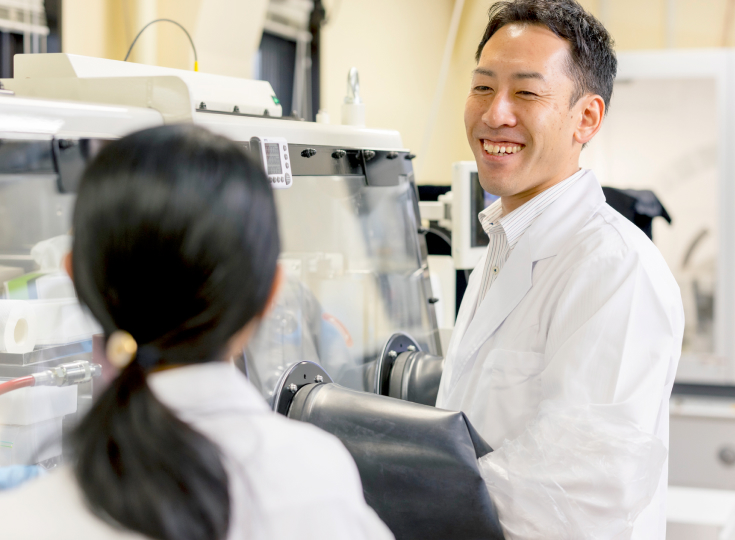
海外での研究経験が今の研究に役立っていると思うことは何でしょう?
誰もやらない研究は大事ですが、世界の研究者が課題にしている、世界の潮流にのった研究をすることも大切です。そういう意味では、アメリカやドイツでの研究経験は、人脈も広がり、考え方の幅も広がる非常に有意義な体験でした。国による文化の違いはあっても、科学を通して対話ができるという気づきがありました。世界を相手にすれば「誰と組む?」、「どのアプローチで行く?」、と研究の選択肢が格段に広がります。今、世界中の人を巻き込んで研究を進めていくおもしろさを感じています。
学生さんたちに対してはどのような役割を果たして行こうとお考えでしょうか?
自分自身を振り返ると、さまざまな方からの影響を受け、少しずつ自分ができる範囲を広げ、ここまでやってきました。学部生の時、留学帰りの先生が自信たっぷりに楽しそうに研究をし、その話をしている様子がカッコよく、海外での研究、特にアメリカで学ぶことに興味を持つようになりました。これが研究者として生きることを考える大きな転換点につながったと思います。自分自身が背中で語る研究者から刺激を受けたように、次代を担う人々に少しでもポジティブな影響を与えられるような研究者になりたいですね。
一方、教育者としての役割も果たしていきたいと考えています。研究は日々壁にぶち当たります。毎日が課題解決の連続で、頭をものすごく使います。何を勉強し、だれに相談し、何のツールを用い、何のパラメータを変え、それらの結果をどのようにまとめ、次に何をするのか、さまざまな角度から課題解決への手段を模索し続けることになります。研究の課題をどこに設定するかも、極めて大切です。背景を把握し、今必要なものを見出して課題として設定し、それを解決しに行く。これはビジネスでも同じだと思います。幅広く応用可能な、考え続けるための基礎体力を訓練し、誰の足跡もないところに足を踏み入れていく、そんな専門以外でも活躍できる人材を育てる…というのは私が教育者として提供できるものの一つだと思います。

PROFILE
学位
Ph.D.:California Institute of Technology, Materials Science
専門分野
材料科学、固体イオニクス、無機化学
主な経歴
| 2012年 | 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科卒 |
|---|---|
| 2012年 | California Institute of Technology, Research assistant |
| 2015年 | Northwestern University, Visiting scholar |
| 2017年 | California Institute of Technology, Materials Science, Ph.D. 取得 |
| 2017年 | Justus Liebig University Gießen, Scientific researcher |
| 2019年 | Justus Liebig University Gießen, Humboldt research fellow |
| 2020年 | 九州大学 大学院工学研究院 応用化学部門 助教 |
| 2023年 | 九州大学 大学院工学研究院 応用化学部門 客員准教授 |
| 2023年 | 東北大学 多元物質科学研究所 准教授 |





